山奥の竹林のそばにかぐや姫というあだ名の老婆が一人、住んでいる。なめらかな肌と切れ長の目が美しかった時分からいつも月を見ていた。縁側に座って見あげる顔は、月の光を浴びて白く輝いていたという。
夏休みで子供を連れて帰省した女に、ついてきた夫がある。かぐや姫のうわさを知らず、なんの気なしに竹林のあたりを通り過ぎようとした。満月の夜だった。
灯りのない田舎家から老婆の声が、
「虹を見かけませんでしたか」
と尋ねかけた。藁葺
《わらぶ》きがしゃべったようで、男は飛びあがった。かきねごしに振り返ると、縁のうえにちょこんと座る者がある。
「虹……。虹は見かけませんでした。こんな夜ではなおさらに……」
長い間があった。男はそこに失望があるのを読みとった。
「なぜ虹が気になるんでしょう」
「月の虹を見るまでは、わたしは死ぬことができません」
「それはなぜ」
竹が風にざわめいた。老婆は背後の闇へ向かって、
「お母さん、寒くない」
と尋ねかけ、沈黙を聞きとってから向き直った。
「わたしはむかし、賢くて美人でしたよ」
「はい」
「話が長くなるかも知れないから、こちらへ来て座ってはいかが」
老婆はかきねの戸口へ向かって手を伸べた。それはちょうど男が立っているすぐ前だ。
「それじゃ遠慮なく」
荒れてさびれた庭のようすは薄闇でも見てとれた。縁の廊下に月明かりが反射してぼうと光る。腰をおろすとひんやり心地よく、かすかな草のざわめきが耳を打つ。
「ここは本当に月がよく見えますね」
「はい」
「月で虹がかかるのですか」
「かかります」
老婆はそう答えてから少し考え、
「かかるという話です」
と言い直す。
「わたしは絵でしか見たことがありません。真っ白な虹がかかるということです」
「ほう」
「とてもきれいな絵でした。子供向けの絵本だったのに捨てられなくて、今でもそれを持っています」
「ロマンチストなんですね」
身じろぎの気配があった。
「そんな誉められたものではありません。月の虹を見るために、こうして夜は月の出ているあいだじゅう目を覚まし、お天道さまのうちは眠るのです」
二人はそろって月を見あげた。よく冴えた十五夜だ。男は急に、
「ああ、うさぎが見える!」
と叫んだ。
「本当にもちをついているように見えるんですねえ。今日はじめて見ましたよ。子供のころはいくらその気で見ても見えなかったのに。こりゃあでっかいうさぎだなあ」
「それは良かったこと」
老婆は声をあげて嬉しそうに笑った。
はじけたような熱が失せると、辺りのかすかな音が迫ってくる。バッタの跳ねるのが分かった。やがて男は口を切った。
「どうしてそうまでして月の虹を見たいんですか」
「むかし賢くて可愛いと言われたからですよ」
「はい……?」
「ある人にね、言われたんです。あなたはそんなに物知りで、そんなに綺麗でちやほやされているけれど、月の虹をその目で見たことがあるんですかって」
男は首を傾げて答えなかった。老婆は物思いにふけったようすをしていたが、じきに続けた。
「男の方がいましてねえ」
「ああ」
「好きになりました」
「はい」
「気をひきたくてね。たまたまその人が月の虹の話をはじめたときに、そばへ寄っていきました」
「仲良くなれましたか」
微笑みが返ってきた。
「いいえ」
「…………」
「つきにじをたった一度だけ見たことがある。それはもう綺麗な白い虹だったとその人が話しているときに、ついうっかり言ってしまったんです。ああ、あれは月虹
《げっこう》と読むのですよと」
男は老婆の方へ顔を向けてじっと見つめた。しわに小さくうもれた眼
《まなこ》が光り、なぜかそこだけ若く見える。
「それで、だったら見たことがあるか、と言われたのですね」
「そうでしたねえ」
キリキリと夏の虫が鳴く。薄雲が満月のうさぎを覆って、辺りが暗くなった。
二人はしばらく黙った。パタパタと子供たちの足音がして、かきねの外に小さな影がふたつ現れた。
「あ、お父さんここにいる」
おかっぱ頭を振りながら少女が指さした。
「ほんとだ、ここにいる!」
「かぐや姫のうちにいたんだ」
「おや、いらっしゃい」
「月の虹は見えたの、かぐや婆ちゃん?」
「なかなか見えないねえ」
「月で虹なんか見えないよ。婆ちゃんだまされてるんだよ」
「婆ちゃん結婚したらいいんだわ」
老婆は笑った。
「まあまあ、こんなお婆ちゃんが結婚するの?」
それから奥の間へ向かって、
「お母さん、今日はお客さんがたくさん来たわ」
と声をかけた。子供たちはシーンとなった。
「お父さん、帰ろうよ」
年長らしき少女が不安げに口を開く。
「月の虹なんかかからないよ。雨ふってないもん」
「おお、そうかい」
「雨ふってもかからないよ」
「そうかい」
男は立ちあがり、
「お邪魔をしました」
と言った。奥の部屋にふとんが敷いてあるのが白っぽく見える。
「お母さんもお大事に」
「はい、ありがとうございます」
子供たちを促してかきねの戸口に手をかけると、男は思い出したように振り返った。
「ああ、そうだ……。虹を見るなら月を見ちゃいけませんよ」
「え、月はだめですか」
「あれは光とは反対の方にかかるものですから」
老婆はしばらく黙ったあと、転がるように笑い出した。ひどく高くよく通る声だ。笑いながら声だけが段々に若返っていき、竹林の暗がりからこだまが返っているかのような奇妙なうねりになっていった。
「そうでした、わたしとしたことが!」
父子が驚いて見ているまえで、なおも老婆は笑い崩れている。
「村でいちばん頭の良い娘と言われていたあのころには、こんな間の抜けた間違いは絶対にしなかったでしょうよ!」
子供が飛び帰ってきたかと思うと、父親の腕をしっかりつかんだ。
「帰ろう、お父さん!」
言われるままに細い手に引かれて出ていこうとすると、かぐや姫は膝立ちになって月の光を浴びていた。
「これでやっとお迎えが来る」
男が妻子とともに帰る前日、村では葬式が一件あった。かぐや姫が死んだのだ。数珠を握って寺へ出向くと、祭壇の中央には二十歳前後の美しい娘の遺影が飾られてあった。
「一日じゅう家探ししたけど、あれしか写真が残ってなくてなあ」
と村の者は言う。
となりに座った老人が話しかけてきた。若いころは大工をしていたというだけに、でこぼこと迫力のある手の持ち主だ。
「かぐやの婆さまが人間だったころの写真だよ。キレイだったねえ」
人間だったころというと? 男は目で問いかけた。
「失恋して毎晩月を見て泣くようになる、そのまえのことよ。俺ぁあのころ、惚れてたね」
かぐや姫になってしまった老婆に寝たきりの母親がいたらしいことを思い出して、男はほかに身寄りがあるのかと尋ねてみた。もと大工は首を振った。
「そんなものはいやしねえ。ふとんに寝ていたのは、あすこに飾ってあるあの写真よ」
「そうでしたか」
男は前かがみに立ちあがり、焼香の列に加わろうとして気がついた。
「ああそうだ」
「なんだい」
「あのお婆さんの遺品の中に、絵本がありませんでしたか? 白い月の虹が描いてある。あれをぜひお棺にいれてあげてください」
老人は手を振った。
「おおそうだった。そのつもりで持ってきてはいるんだ。よけりゃ棺に入れるまえに眺めて行きなよ」
老婆が最後まで手元においた絵本の中には、墨で描かれた月の虹がかかっている。粗末なつくりでお世辞にも美しいとは言いがたい。
すすけたぼろ紙のうえで、それでも虹は月長石のようにぼうっと光っているのだった。
(イラスト:Studio Blue Moon 蒼い猫さん)
2002.7.11
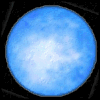 月の虹
月の虹